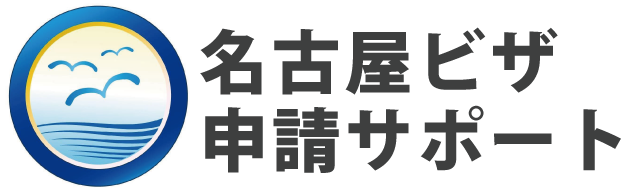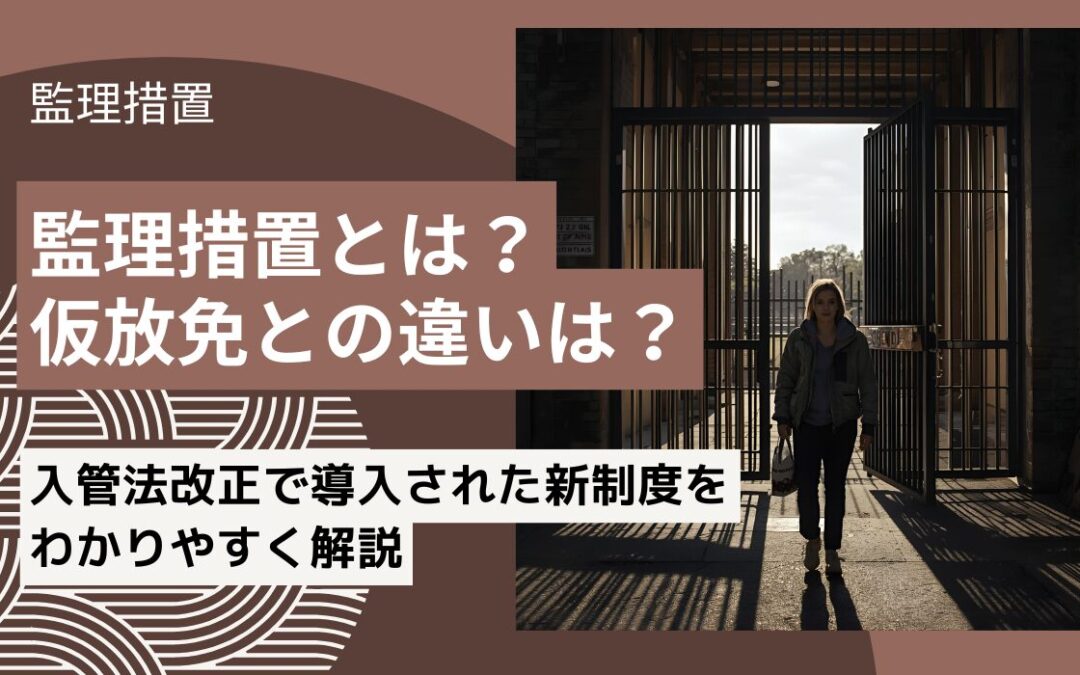外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。
2024年6月、入管法(出入国管理及び難民認定法)が改正され、新たに「監理措置(かんりそち)」が導入されました。
これは、従来の「収容」に代わる仕組みとして注目されています。
本記事では、監理措置の概要から要件、条件、そして「仮放免」との違いまで、専門知識がない方にもわかりやすく解説します。
目次
監理措置とは?入管法改正で新設された「収容に代わる措置」
監理措置とは、外国人を収容せずに退去強制手続を進めるための新たな制度です。
監理人の監督のもとで社会生活を続けながら、逃亡や証拠隠滅を防止する仕組みになっています。
この制度は「退去強制令書発付前」と「発付後」の両段階で運用されます。
監理措置の要件
監理措置を受けるには、次の条件を満たす必要があります。
-
監理人が選定できること
-
主任審査官が、逃亡や証拠隠滅のおそれ・健康状態・家族状況などを総合的に考慮し、収容しないでの手続を適当と認めること
これにより、人道的な配慮と社会的な安全の両立を図ります。
監理措置の条件と罰則
被監理者(監理措置の対象者)には、住居・行動範囲の制限や、呼出しへの出頭義務などが課されます。
また、主任審査官の判断で、最大300万円の保証金が条件となる場合もあります。
違反した場合の罰則も明確に定められており、
-
逃亡や呼出し不応:1年以下の懲役または20万円以下の罰金
-
監理措置決定通知書の不携帯:10万円以下の罰金
が科される可能性があります。
被監理者の届出義務
被監理者は、3か月以内ごとに指定された日に、
所属する地方出入国在留管理官署へ以下を届け出なければなりません。
-
監理措置条件の遵守状況
-
就労許可を受けて行った活動内容 など
これにより、制度の適正な運用と監督が維持されます。
就労(報酬を受ける活動)の許可
原則として、在留資格がない外国人は働けません。
ただし、退去強制令書がまだ発付されていない場合で、生計維持のために必要かつ相当と認められるときには、限定的な就労許可が認められることがあります。
一方、退去強制令書発付後に報酬を得る活動を行った場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金などの厳しい罰則があります。
監理措置と仮放免の違い
監理措置制度の新設により、仮放免が認められる範囲は大幅に限定されました。
現在では、健康上・人道上の特別な事情など、やむを得ない場合に限って仮放免が許可されます。
原則として、収容を解除する際の基本的な手段は監理措置です。
注意点:監理措置=在留の合法化ではない
監理措置が決定されたとしても、在留が合法化されるわけではありません。
あくまで退去強制手続を「収容せずに進める」ための制度です。
制度の誤解によるトラブルを避けるためにも、専門家への相談をおすすめします。
まとめ(結論)
-
監理措置は、入管法改正で導入された「収容しない退去手続」の仕組み
-
被監理者には一定の制限と義務が課される
-
仮放免は原則的に限定的な運用に変更
-
監理措置を受けても在留資格が与えられるわけではない
監理措置に関するご相談
監理措置の申請や手続き、仮放免との違いなどについてお困りの方は、当社までお気軽にご相談ください。
専門家が制度のポイントを丁寧にサポートいたします。
関連記事
関連ページ
外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。