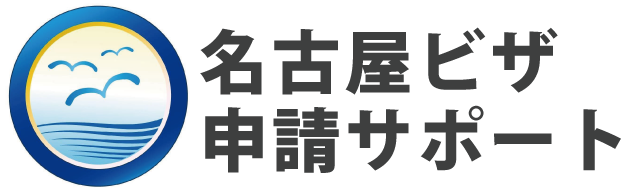外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。
「難民申請の手続きが複雑すぎる」「難民認定はほとんど通らないって本当?」――そんな疑問や不安を抱える方も多いのではないでしょうか。本記事では、日本における難民認定制度の現状、実際の認定数、就労資格との関係、そして現場で直面する課題について初心者の方にもわかりやすく解説します。
目次
難民認定とは?国際条約に基づく定義
難民とは、1951年の難民条約第1条に基づき、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団または政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあると合理的に恐れているため、自国の保護を受けられず、またはそれを望まない者」と定義されています。
【最新統計】日本における難民申請と認定の実情
出入国在留管理庁の公表によると、令和5年度の難民認定申請者は13,823人。主な出身国はスリランカ、トルコ、パキスタン、インド、カンボジアなどで、申請者は87か国に及びます。
このうち、実際に在留を認められたのは1,310人。その内訳は以下の通りです:
- 難民として認定された者:303人
- 人道的配慮により在留が許可された者:1,005人
認定された方は、日本国民と同様の社会保障や支援を受けることが可能です。
難民申請者が抱える就労の課題と現場の対応
難民申請中でも、日本で「特定活動」の在留資格により滞在している方がいます。中には、就労可能な特定活動資格を持つ方もいますが、多くは3〜6か月ごとの短期更新であり、生活の安定が難しいのが現状です。
そのため、より安定した「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労資格への変更を希望する相談が増えています。しかし、申請には学歴や職歴などの厳しい条件をクリアする必要があるため、慎重な対応が求められます。
【現場の声】支援の限界と向き合う行政書士の実情
帰国できない事情を抱えた外国人に寄り添い、日本での生活をサポートすることは、私たち専門家の大切な使命です。しかし、難民申請中や認定が難しいケースでは、十分な支援ができないもどかしさもあります。
申請希望者の背景や個別事情に寄り添い、法的に適正な範囲で支援する姿勢が、今後ますます求められるでしょう。
用語解説(初心者向け)
| 用語 | わかりやすい説明 |
|---|---|
| 難民条約(1951年条約) | 国際的に難民の保護を目的とした条約。日本も加盟しており、誰を難民と認めるかの基準を定めています。 |
| 難民認定 | 「この人は難民です」と日本政府が正式に認めること。認定されると長期滞在が可能になります。 |
| 特定活動 | 特別な目的のために一時的に日本に滞在する在留資格。内容によっては就労可能です。 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 専門的な知識を活かした仕事をするための在留資格。例:会社員、翻訳、マーケティング職など。 |
| 特定技能 | 介護や建設など人手不足の分野で働くための在留資格。一定の試験や日本語力が必要です。 |
| 人道的配慮 | 難民には該当しないが、人道的理由で在留が許可されるケース。例:帰国すると命の危険がある場合など。 |
| 出入国在留管理庁 | 外国人の出入国や滞在を管理する日本の行政機関。以前の「入国管理局」が組織改編されてできました。 |
| 補完的保護対象者 | 難民ではないが、戦争などにより保護が必要とされる人。ウクライナ避難民などが該当します。 |
関連ページ・参考リンク
著者情報|みなと行政書士法人
外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。
外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。