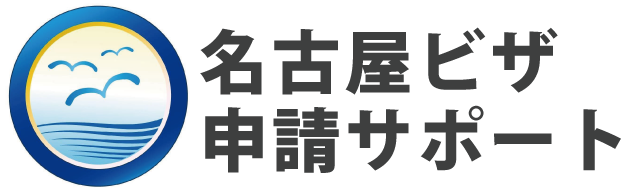外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。
建設業界において外国人労働者の活用は年々増加しています。しかし、採用時には業務内容に応じた適切な在留資格を取得することが重要です。不適切な資格での就労は、企業側にも法的リスクが発生するため、慎重な対応が求められます。
本記事では、建設業における主要な在留資格と、それぞれの対象業務について詳しく解説します。
主な在留資格とその適用範囲
1. 技術・人文知識・国際業務
この資格は、大学や専門学校で建築や土木に関する知識を学んだ外国人、または10年以上の実務経験がある外国人が取得できます。
✅ 対象業務
- 法人営業(建設業界向けの営業・マーケティング業務)
- 建築設計やプロジェクトマネジメント(一定の実務経験が必要)
❌ 注意点
以前は、建設現場の「職長・班長レベルの指導・監督業務」も対象とされていましたが、現在は現場作業が含まれる場合は認められにくくなっています。
2. 特定活動(本邦大学卒業者)【告示46号】
この資格は、日本の大学や大学院を卒業した外国人が対象です。
✅ 対象業務
- 建築現場での外国人従業員への指導・通訳業務
- 現場作業の一部(ただし、学んだ建築知識を活用する必要あり)
❌ 注意点
- 高い日本語能力(通常N1以上)が求められる
- 入国管理局による厳格な審査が行われる
3. 特定技能1号(即戦力労働者向け)
特定技能1号は、一定の技能試験に合格した外国人労働者が取得できる在留資格です。
✅ 対象業務
- 仮設建築物の設置や掘削、土止め工事
- 躯体工事(建物の骨組みを作る工事)の組立てや解体作業
❌ 注意点
- 在留期間は最長5年(家族帯同不可)
- 雇用する企業は外国人支援計画を策定し、適切な支援を提供する義務がある
4. 特定技能2号(熟練労働者向け)
特定技能2号は、高度な技術・経験を持つ外国人が取得できる在留資格で、特定技能1号よりも業務範囲が広がります。
✅ 対象業務
- 建設現場の管理業務(工程管理・品質管理)
- 仮設建築物や掘削、躯体工事の指導・監督
❌ 注意点
- 在留期間に制限なし(更新可能)
- 家族帯同が可能
5. 技能実習(技術習得を目的とした在留資格)
技能実習は、発展途上国の外国人が日本の技術を学び、母国へ持ち帰ることを目的とした制度です。
✅ 対象業務
- 木造建築、土木工事の段取り作業
- 足場の設置・解体、掘削、基礎工事
❌ 注意点
- 最長5年間の滞在(技能実習3号まで更新可能)
- 企業は技能実習計画を作成し、監理団体の指導を受ける必要がある
外国人採用時の注意点
✅ 1. 業務内容に合った在留資格を確認する
→ 適切な資格を取得しないと、不法就労と見なされる可能性があります。
✅ 2. 就労可能な範囲を明確にする
→ 例えば、「技術・人文知識・国際業務」では現場作業は不可ですが、「特定技能1号」では可能です。
✅ 3. 行政書士などの専門家に相談する
→ 外国人の在留資格申請は専門的な知識が必要なため、手続きに不安がある場合は行政書士に相談することをおすすめします。
まとめ
建設業で外国人を採用する際には、業務内容を明確にし、それに適した在留資格を取得することが不可欠です。特定技能・技能実習・技術・人文知識・国際業務など、在留資格ごとの適用範囲を把握し、適切な手続きを行いましょう。
外国人採用のサポートが必要なら、みなと行政書士法人にご相談ください!
行政書士が、在留資格の取得から労務管理までしっかりサポートします。
外国人の在留・ビザ・帰化手続きに強い行政書士法人。英語・中国語・ベトナム語・インドネシア語対応・全国対応で、外国人の方の日本での生活をサポートしています。
実務経験に基づいた信頼性の高い情報をお届けします。